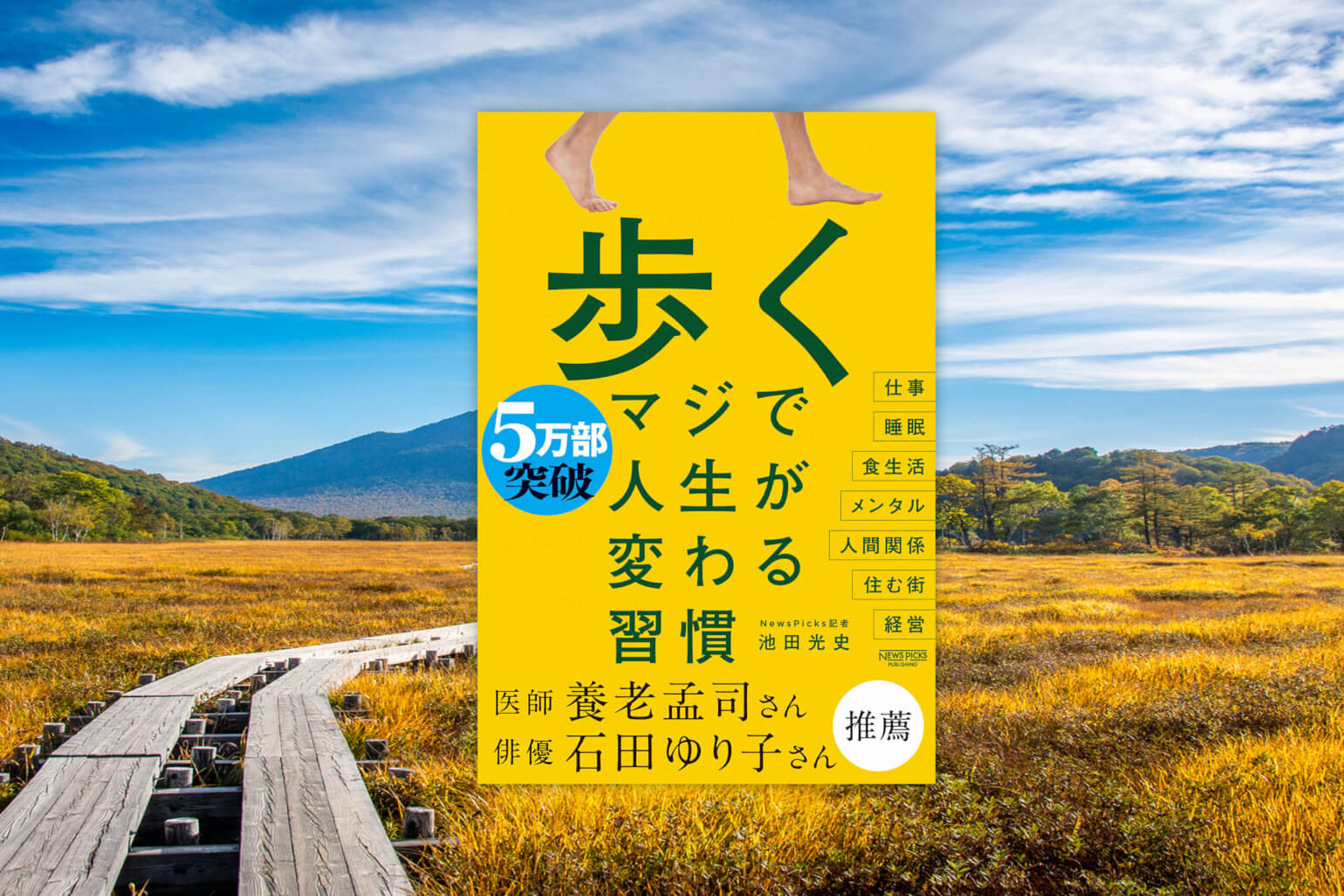【後編】『歩く マジで人生が変わる習慣』の一部を無料公開
“偉業をなす人は、「歩く」にたどりつく。”
気づけば歩かなくなっている──。
そんな現代社会のしくみに無自覚だったNewsPicks記者の池田光史氏が、自らの身体感覚を取り戻していく経験を通じて、歩くことが人間の脳や身体とどうつながっているか、最新のデータや論文を片手に深く迫った『歩く マジで人生が変わる習慣』(NewsPicksパブリッシング)。
俳優の石田ゆり子さんや、医師・解剖学者の養老孟司さんも推薦する、「歩く」を徹底解剖した書籍の一部を、特別に無料公開。
後編では第2章の後半として、「歩く」の深掘りを通じて得たさまざまな考察・エピソードと、今日から実践できる3つのTIPSをお届けします。
【前編】『歩く マジで人生が変わる習慣』の一部を無料公開 はこちら
2025.08.11
YAMAP MAGAZINE 編集部
INDEX
アップルウォッチで強調されたこと
ところで、Step 1(第1章)で触れた、シリコンバレーに根付いているというウォーキングミーティングについて取材の歩みを進めていくと、いかに都市化が人体実験といえるのか、そして「歩かないがゆえの新しい問題」というテーマと交差する、面白いエピソードにたどり着く。
「座ることは新しい喫煙である」(Sitting is the new Smoking.)
これは、2014年にアップルがウェアラブル端末「アップルウォッチ」の発表時に、1時間に1回立ち上がるように通知する新機能「スタンド」をお披露目する際、CEOのティム・クックが繰り返した有名な言葉だ(より正確には、彼はときどき「座ることは新しいがんである」という言い方もしている(※6))。その後、世界中で実に4億回以上も引用されているのだという(※7)。
実は、この言葉をもともと考案したのは、ティム・クック自身ではない。このフレーズが世に送り出されたのは、2013年に公開された、あるTEDトークの最中のことだった。
その話者は、ニロファー・マーチャント。アドビなどテック企業の元幹部で、現在はビジネスリーダーシップやイノベーション分野の著名な思想家として活躍する人物だ。
Thinkers50の「未来の思想家」賞や、英HRマガジン社のトップ10のHR思想家にも選出されていて、影響力を持つコンサルタントでもある。
面白いのはここからだ。TEDトークで上位10%の再生数となった彼女の講演タイトルこそが、次のようなものだった。
「会議がある? 歩きましょう」(Got a meeting? Take a walk)
その内容はこうだ(※8)。僕たちは、平均して1日9.3時間も座っている。これは、睡眠の7.7時間より長い。だから、会議室でミーティングをするのではなく、誰もが歩いてミーティングすべきだ、と。
より詳しい要点を紹介しておこう。ここでも、創造力が向上することが指摘されている。
①座ることの健康リスク:長時間座ることは危険性をはらむ。心臓病や特定のがん、2型糖尿病などの深刻な健康問題と関連しており、新しい「喫煙」と同等である
② 変化のきっかけ:マーチャントは、ウォーキングミーティングに招待されたことをきっかけに、座りがちな生活を変えた。この斬新な会議の方法が彼女に大きな影響を与え、彼女は定期的にウォーキングミーティングを採用するようになった
③ 健康と生産性の統合:ウォーキングミーティングこそが、健康を維持しながら仕事の責任を果たすことを同時に可能にする。健康と仕事のどちらかを選ばなければならないわけではない
④ 創造性と問題解決能力の向上:ウォーキングミーティングは、肉体的な健康を改善するだけでなく、伝統的なオフィス環境の外で新鮮な視点が得られ、創造的な思考や問題解決能力も向上させる

ちなみにマーチャントは、米CNNのインタビューで、こうも述べている(※9)。
ウォーキングミーティングでは、携帯端末が視界に入りません。だから、ミーティングの場から離れようとする誘惑がなく、集中することができます。
スマートフォンやパソコンなどの端末に邪魔されにくいという意味でも、集中して話すには、「一緒に歩く」のが手っ取り早いということだ。
この「一緒に歩く」という行為に関しては、その後、香港大学が興味深い研究の成果を2020年に発表している(※10)。それによれば、一緒に歩く2人組は、たとえ沈黙していても自然とお互いの歩行ペースに合わせることがわかったという。要は一緒に歩くと、お互いに好印象を与える傾向があるのだ。
もっとも、そんなウォーキングミーティングの効果を知ってか知らずか、習慣として取り入れていたジョブズその人が、会話における集中力を阻害するスマートフォンというプロダクトを発明し、僕たちのライフスタイルを一変させた張本人であるのは、奇妙な皮肉にも感じる。
(※6)Stuart Dredge. (2015, Feb 11). “Tim Cook hails Apple Watch health benefits: ‘Sitting is the new cancer’”.The Guardian.
(※7)Niilofer Merchant. “About”.
(※8)Jessica Gross. (2013, April 29). “Walking meetings? 5 surprising thinkers who swore by them”.TED Blog.
(※9)Vanessa Ko. (2013, March 20). “Let’s take a walk: A push for meetings on the move”. CNN.
(※10)Miao Cheng, Masaharu Kato, Jeffrey Allen Saunders, Chia-huei Tseng. (2020). “Paired walkers with better first impression synchronize better”. PLOS ONE. 15 (2).
睡眠より長い「座る時間」

ここでもう一度、マーチャントのプレゼン内容を見てみよう。
僕たちは、1日平均9・3時間も「座って」いる?
さらりと述べられているが、これは驚くべきデータだ。そして、確かにその通りかもしれない。改めて考えさせられる数字なのは、かたや平均睡眠時間が7・7時間だからであり、つまり起きている時間の60%は座っている勘定である。
現代のテクノロジー、すなわちテレビやパソコンなどの出現によって、人類は歴史上、かつてないほど座っている時間が長くなっている。コンピュータゲームもしかり。そして忘れがちだが、車はもちろんのこと、電車やバスに乗って座っているなら、それらの移動時間も加算される。
そして、座っている時間は、都市化が進む高所得国ほど長いということが明らかになっている(※11)。
しかし、僕たちの身体は本来、そのように設計されていない(※12) 。つまり、これほど長時間座り続けるための生物的進化は遂げていないわけだ。生物的な進化は数千〜数百万年単位で起こるとされ、そう簡単に長時間座るための進化を達成するのは期待できない。実際に、長時間の座位は死亡リスクを高めるのである(※13) 。
なによりショッキングな事実は、長時間の座位が続くと、どんなに運動を増やそうとも、そのリスクを相殺するのは難しいということだ。繰り返すが、「どんなに運動を増やそうとも」である。
たとえば、1時間以上連続して座っていると、脂肪を燃焼させる酵素の生成が減少する。身体の代謝は遅くなり、体内の善玉コレステロールレベルに悪影響をおよぼす可能性がある。また、長時間の座位が続くと、心臓病のリスクが6%、2型糖尿病が7%、そして乳がんや大腸がんのリスクが10%増加する可能性があることが示されている。長時間座ったままになると、こうした身体の変化を食い止めることができなくなる、というのである。
しかも、アメリカでタバコを吸うのは成人の約19・8%(約4920万人)(※14) であるのに対し、肥満はその2倍の41.9%だ(※15) 。喫煙率が過去数十年で減少している一方で、座る時間はみるみる長くなっていくことを考えると、座ることは「新しいタバコ」のようなものであるというメタファー(※16) は、あながち間違っていないのかもしれない(※17) 。
そういうわけで、2014年のアップルウォッチ登場も相まって、一定時間座り続けたら立ち上がることや、近年ではスタンディングデスクを使うことも珍しくなくなった。僕はこのアップルウォッチのスタンド機能を無視し続けてきたわけだが、この機能だけでもアップルウォッチを身に着けている価値があるということだ。
ただ、それだけでは足りない。だから座ってばかりのミーティング中にこそ、歩こう、というわけだ。
一般に、成人が1時間で歩ける距離は4〜6㎞、歩数にして6000〜7500歩ほどだ。そう考えると、1時間の会議1回分だけでもウォーキングミーティングに切り替えれば、かなり効果がありそうだということがわかる。
創造力を高めるという効果以上に、そもそも長い時間座り続けている都市生活がいかに異常なのかということは、もっと広く認識されていい。そして、不調を訴える人が増えれば増えるほど、それを解消していこうという文脈のほうが、ウォーキングミーティングの導入をより本格的に後押ししていくのかもしれない。
(※11) M. Mclaughlin, A. J. Atkin, L. Starr, et al. (2020). “Worldwide surveillance of self-reported sitting time: a scoping review”. International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 17(111).
(※12) Vytas SunSpiral. (2011). “Office Ergonomics: Why Sitting Will Kill You”. BeingHuman.
(※13) Ulf Ekelund, et al. (2016). “Does physical activity attenuate, or even eliminate, the detrimental association of sitting time with mortality? A harmonised meta-analysis of data from more than 1 million men and women”. The Lancet.
(※14) U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2024). “Current Cigarette Smoking Among Adults in the United States”. Smoking and Tobacco Use.
(※15) U.S. Centers for Disease Control and Prevention. (2024). “Adult Obesity Facts”. Obesity.
(※16) 脚注4と同.
(※17) E. G. Wilmot, C. L. Edwardson, F. A. Achana, M. J. Davies, T. Gorely, L. J. Gray, K. Khunti, T. Yates & S. J. H. Biddle. (2012). “Sedentary time in adults and the association with diabetes, cardiovascular disease and death: systematic review and meta-analysis”. Diabetologia. 55(11), 2895-905.
ホモ・セデンタリウス

10年ほど前、僕は初めて高額な椅子に自己投資した。ハーマンミラーのアーロンチェアである。職業柄、パソコンの前に座って原稿を書く時間が長く、痛めつけられた腰を守るためだった。この投資は見事に的中し、腰の痛みは消え、いまも変わらず僕の仕事を支え続けている。
だが、この人間工学の結晶とも言うべき椅子の快適さは、より本質的な問いを僕から覆い隠していた。そもそもの発想が間違っていたのだと気づかされたのは、イギリスの医師であり研究者でもあるジェームス・レヴィンの論文に出会ったときだった。
私たちは、椅子中心の世界を設計してしまった。それは間違いだった。
彼の論文のタイトルには、実に示唆に富む「造語」を含んでいた。
「座りすぎという死の習慣:ホモ・セデンタリウスは答えを探る」
(Lethal Sitting: Homo Sedentarius Seeks Answers)
Sedentaryとは「座位の、運動不足の」という意味だが、このホモ・セデンタリウスという造語は、現代人の姿を実に巧みに表現している。それは単に、セデンタリー・ライフスタイル(座位中心の生活様式)を示すだけではなく、「ホモ・エレクトス」(直立するヒト)という人類進化の重要なステップを想起させ、獲得した直立二足歩行を活かさずに座り続ける現代人を皮肉っているように聞こえるからだ。
さらに、狩猟採集民から定住へ、そして「デスクへの定住」へと至った人類の歩み─ある意味での退化─という比喩も重層的に宿している。しかも、なぜそうなってしまったのか、その原因を「座りながら」探求しているのが現代人だ、と。
産業革命以前(90%は肉体的に活発な農業従事者だった)、人類は1日3時間ほどしか座らなかった。それが気づけば都市居住者となり、僕たちは1日10〜15時間も椅子に縛られている。レヴィンによれば、そうした変化は4世代にわたって、繁栄という甘い誘惑とともにゆっくりと進行していったという。その間に、都市化、工場労働、オフィスワーク、自動車、スクリーンの娯楽─これらが静かに、確実に僕たちのライフスタイルを変えていった。
そして彼もまた、座り続けることによる身体への影響は、タバコよりも深刻かもしれないと言う。それは人体への害が広範囲におよぶからで、これまで述べてきた通り、肥満、代謝異常、心臓病、がん、精神疾患にまで至る。
僕たちは直立二足歩行を獲得し、解き放たれた手が道具を生み、文明を築き上げた。しかしその果実は、ただ僕たちを椅子に縛り付けることだったのだ。もっとも、その解決策は至ってシンプルだ。立ち上がって、歩くことである。
コラム マジで人生が変わる:健康を保つ習慣

ホモ・セデンタリウスから脱却し、健康を保つための方法を、本文で紹介した論文たちを基にまとめておこう。
1.座る時間をこまめに中断する
座る時間が長いと、肥満、代謝異常、心疾患、がんのリスクが増加し、精神にも悪影響だ。血糖値の管理や筋肉の健康維持のためにも、毎時間、数分間立ち上がったりストレッチをしたりするだけでもいい。僕はミーティング中に1回は立ち上がるようにしている。スタンディングデスクの導入も一つの手かもしれない。電車の中でも立ち上がる時間を。
2.食後に歩く
食後に15分ほどゆっくり歩くだけで、食後血糖値の急激な上昇(血糖変動)を半分に抑えることができる。血糖値を安定させることにつながり、ひいては糖尿病予防に有効だ。ランチやディナーの帰りは必ず1駅歩く、といった習慣を取り入れるといい。
3.日常的な身体の動きを増やす
「非運動性熱産生(NEAT)」と呼ばれる、日常生活での身体の動きを増やすといい。通勤や買い物の際に歩く、エスカレーターやエレベーターは使わずに階段を使う、というだけでもだいぶ変わってくるはずだ。
【前編】『歩く マジで人生が変わる習慣』の一部を無料公開 はこちら
『歩く マジで人生が変わる習慣』
池田光史著『歩く マジで人生が変わる習慣』(NewsPicksパブリッシング)
【実践】靴が変わると、歩きたくなる。
本書の出版記念イベントとして開催された、YAMAP春山、ALTRAジャパンの福地孝氏との鼎談の模様を収録した記事もぜひお読みください。
▶︎【実践】靴が変わると、歩きたくなる。(NewsPicks)を読む
画像:PIXTA